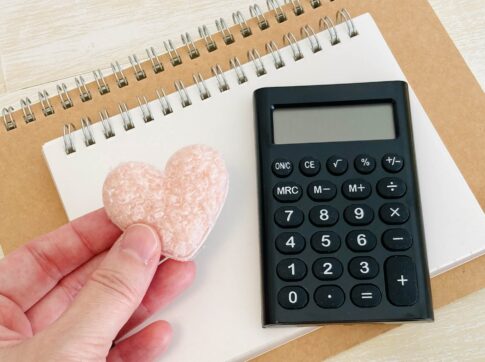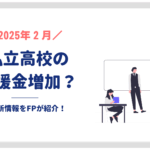2019年に始まった幼児教育・保育の無償化に続き、2025年からは義務教育である小中学校の学校給食費まで公費負担になる可能性があります。これにより、子育て世帯の経済的負担はさらに軽減されることが期待できます。とはいえ、教育費以外にも様々な支出があります。
ここでは、2025年からの教育費無償化の変更点を確認しつつ、今から始める貯蓄方法をファイナンシャルプランナーの視点から詳しく解説していきます。
(※2025年1月17日現在の情報を基に執筆)
教育費とは
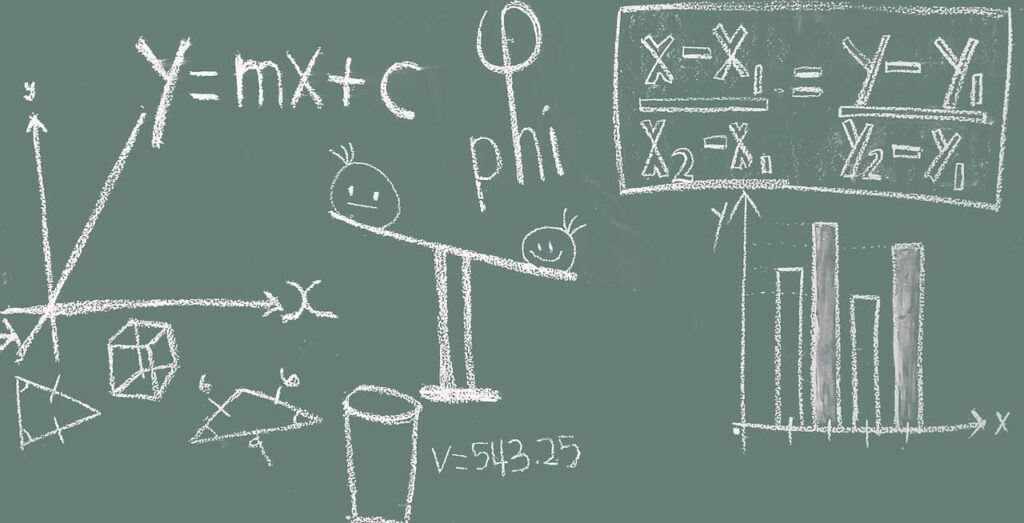
教育費とは、入学費や授業料だけでなく、給食費や塾、習い事などに関する費用も全て含まれる費用を指します。
| 教育費 | 学校教育費 | 入学金や授業料など |
|---|---|---|
| 学校給食費 | 給食費 など | |
| 学校外活動費 | 塾や習い事 など |
参考:文部科学省「子供の学習費調査」
※調査では「学習費」という名称で表記していますが、本記事では「教育費」という名称で統一します。
教育費無償化制度とは
教育費無償化制度は、教育にかかる家庭の経済的負担を軽減し、誰もが希望する教育を受けられる社会の実現を目指しています。現在は乳幼児を対象とする「幼児教育・保育の無償化」と高校生などを対象とする「高等学校等就学支援金制度」があります。
さらに2025年度(令和7年度)からは、多子世帯の学生を対象に大学等の授業料等の無償化も決定しました。
【乳幼児】幼児教育・保育の無償化制度
対象
3~5歳のすべての子どもと、0~2歳の住民税非課税世帯の子ども
助成内容
- 幼稚園、保育所、認定こども園:無償(子ども・子育て支援制度対象外の幼稚園は月額25,700円まで)
- 預かり保育も一定の上限内で無償
- 認可外保育施設等は月額3.7万円まで無償(さらに住民税非課税世帯は0~2歳で月額4.2万円まで無償)
【高校生】高等学校等就学支援金制度
対象
日本国内の高等学校(全日制、定時制、通信制)や特別支援学校高等部に在学する生徒。
(ただし、所得要件あり。)
助成内容
- 公立高校:全日制で年間最大118,800円 が支給(実質的に授業料が無償化される仕組み)
- 私立高校:全日制で年間最大396,000円が支給(通学形態や所得などで金額が変化)
【大学生等:2025年度開始】高等教育の修学支援新制度
対象
子どもが3人以上いる世帯(多子世帯)で所得要件はありません。
助成内容
- 国公立大学:授業料54万円、入学金28万円が減免
- 私立大学:授業料70万円、入学金26万円が減免
※専門学校や短大などの大学以外の教育機関は、校種・設置者ごとに設定されます。
2025年度 教育費無償化の変更点

2025年度から、教育費無償化の対象が拡大されることが決定しました。主な変更点は以下の通りです。
【決定】大学授業料等の無償化
上記の通り、2025年度から多子世帯の学生を対象に大学の授業料や入学金が減免される予定になります。最大で年間70万円が無償化されるため、経済的な負担が大きく緩和されることが期待されます。
特に2024年9月に東京大学で20年ぶりに授業料の値上げが発表されたこともあり、昨今の教育機関の授業料に関するテーマは過熱しています!
【未定】高校授業料の無償化の拡充
現在、高校の無償化制度(高等学校等就学支援金制度)はあるものの、所得制限が設けられています。
所得制限
| 保護者の働き方 | 子の人数と学年 | 118,800円の支給(年収目安) | 396,000円の支給(年収目安) |
|---|---|---|---|
| 両親のうち一方が就労 | 高校生2人 | 約950万円以下 | 約640万円以下 |
| 大学生1人、高校生1人 | 約960万円以下 | 約650万円以下 | |
| 共働き | 高校生1人、中学生1人 | 約1,030万円以下 | 約660万円以下 |
| 高校生2人 | 約1,070万円以下 | 約720万円以下 | |
| 大学生1人、高校生1人 | 約1,090万円以下 | 約740万円以下 |
文部科学省「高等学校等就学支援金」を参考に作成
この所得制限について、日本維新の会は2025年1月10日の自民、公明両党との実務者協議にて、「2025年4月からの所得制限」を設けずに高校授業料を無償化するよう要求しました。
本記事執筆時点(2025年1月17日)からあと3ヵ月弱ともあり、4月からの実現は難しいのではないかと個人的には思いますが、場合によっては近い将来、高校の無償化制度に所得制限が撤廃される可能性もあるため紹介しました。
東京都と大阪府は独自で所得制限を撤廃
既に東京都と大阪府では、2024年度から独自で所得制限の撤廃と助成金の上限引き上げが行われています。
教育費に備える方法
教育費無償化は、全額が無償化されるわけではないため、一定の教育費は備えておく必要があります。文部科学省が公表した「令和5年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から高等学校までの各学校種別における1年間の学習費総額は以下の通りです。
| 学校種別 | 公立 (円) | 私立 (円) |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 184,646 | 347,338 |
| 小学校 | 336,265 | 1,828,112 |
| 中学校 | 542,475 | 1,560,359 |
| 高等学校 | 597,752 | 1,030,283 |
さらに、幼稚園3歳から高等学校卒業までの15年間に必要な学習費の総額は以下の通りです。
| 通学パターン | 総額 (円) |
|---|---|
| 全て公立に通った場合 | 約5,320,000 |
| 幼稚園のみ私立、他は公立の場合 | 約7,760,000 |
| 幼稚園と高等学校が私立、小・中学校が公立の場合 | 約10,970,000 |
| 全て私立に通った場合 | 約19,760,000 |
いずれも、文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」を参考に作成
公立と私立で約4倍近くの乖離があります。お子さまのご希望や貯蓄などを考慮して、教育費として備えておくべき金額を検討しましょう。
学資保険
学資保険は、子どもの入学資金を準備するための保険で、進学時期に合わせて満期を設定し、保険金を受け取ることができます。
親が契約者となり、もし契約者が死亡または高度障害状態になった場合でも、それ以降の保険料の払込みが免除され、満期まで引き続き契約を継続できる点が特徴です。
まとまった教育費の支出まで時間に猶予がある場合は、学資保険を活用しながら計画的に教育費を貯めておくという手があります。
教育ローンや奨学金の活用
一方で、教育費の支出まで時間が無い場合は、教育資金に特化した借入制度の活用を検討しましょう。借入制度として、教育一般貸付と奨学金の2つをご紹介します。
| 教育一般貸付 | 奨学金 | |
|---|---|---|
| 契約者 | 親 | 子(学生) |
| 借入可能額 | 1人あたり最高350万円 (海外の大学への留学などの要件を満たせば450万円) | 最高月額184,000円 第一種奨学金(月額64,000円)+ 第二種奨学金(月額120,000円)を併用した場合 |
授業料や入学金だけでなく、生活費などにも充てることができるため、利用しやすい制度といえます。
NISAの活用
NISAの活用も有効です。学資保険と同様、教育費の支出まで猶予がある場合に有効ですが、運用益の非課税という最大のメリットを活用し、計画的に運用していきましょう。
※NISAは2024年1月からの大幅な改正により、口座開設数が増えている制度です。しかし、NISAは投資対象は金融商品であり、元本保証されているわけではありません。
「知るぽると」のシミュレーションツールを活用しよう!
金融広報中央委員会(知るぽると)では、様々なシミュレーションツールが用意されています。教育費などを何年後にいくら貯めなければならないかを可視化できるので、ぜひ活用してみましょう。
金融広報中央委員会(知るぽると)のサイトはこちら
まとめ
2025年度からの教育費無償化の変更点として、大学授業料等の無償化が決定し、多子世帯の学生を対象に最大年間70万円の減免が実施されます。これにより、子育て世帯の経済的負担が軽減されることが期待されます。
しかし、授業料以外の教育費や生活費など、依然として自己負担となる費用も存在します。そのため、これらの制度をしっかりと理解し、各家庭の状況に応じた適切な対策を講じることが重要です。学資保険や教育ローン、NISAなどを活用し、計画的な貯蓄と資金準備をしていきましょう。
お問い合わせ
ご相談等はこちらのフォームよりお願いいたします。


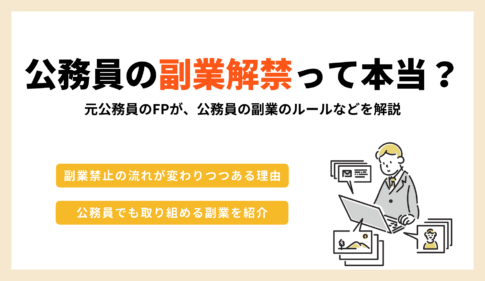
の仕事が無くなる?AIへの代替と将来性-485x323.jpg)