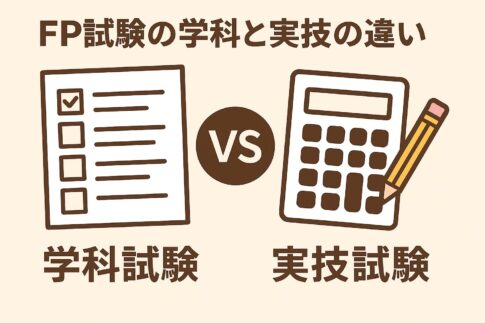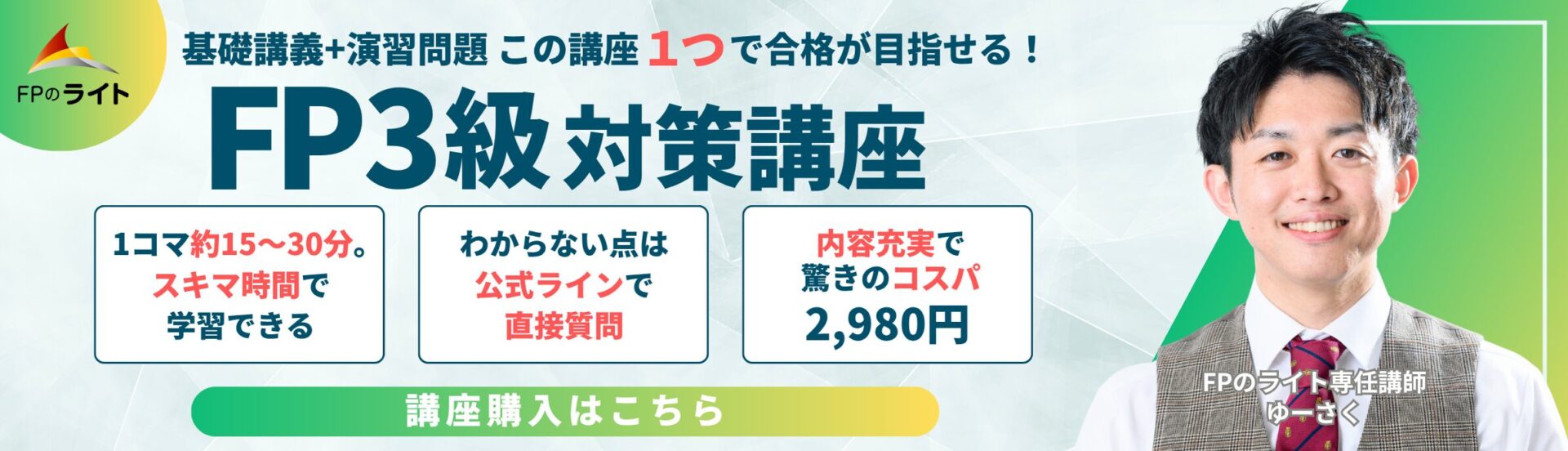近年人気が高まっているファイナンシャルプランナー(FP)は、金融・税金・保険などの生活に役立つ知識が学べることから、受験者数も増えている人気資格の1つです。しかし、「どのように勉強すべきかわからない」「すぐに取得できる資格なの?」と感じる方もいるのではないでしょうか。特に最近は、SNSの普及などで勉強方法が多様化し、何から始めればよいかわからずに無計画で独学で勉強する方も多いはず。
しかし、適切な方法を講じれば独学でも問題なくFP試験に合格できます。そこでこの記事では、FP試験の独学での学習方法、短期合格の学習スケジュールまで徹底解説します。
なお、FPのライトでは格安でFP3級の合格を目指せるコンテンツをご提供しています。
2,980円でテキストと演習問題がセットになっており、わからないところもLINEで質問できる仕組みのため、最小の費用で効率よくFP3級を取得できます。詳しくは以下のボタンをタップ!
2,980円で最短合格!
目次
FP資格は独学で合格できる

先に結論から言うと、FP試験は独学でも十分合格可能です。お金の専門家であるFPの資格を多額のお金をかけて取得するのは本末転倒なので、ぜひ独学で取得したいところです。
ただし、独学で取得できるのはFP2級とFP3級に限られます。理由は次の通りです。
FP試験の受験資格
まず、FP試験に独学で合格できるかをお伝えする前に、FP試験の受験資格からご紹介します。そもそもFP試験はFP1級~3級の国家資格と、AFP、CFPの民間資格があり、次の表の通りに受験資格が定められています。
| 受験資格 | |
|---|---|
| FP3級 | FP業務に従事している者または従事しようとしている者 |
| FP2級 | 以下のうち、1つ以上を満たす場合 ・FP3級の合格者 ・FP業務に関し2年以上の実務経験がある ・AFP認定研修(基本課程)修了者 ・金融渉外技能審査3級(FP試験の前身)の合格者 |
| FP1級 | 以下のうち、1つ以上を満たす場合 ・FP2級合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験がある ・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者 ・金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験がある |
| AFP | 主な方法は、以下のうちいずれかの場合 ・FP2級合格者がAFP認定研修(技能士課程)を修了 ・AFP認定研修(基本課程)修了後にFP2級に合格 |
| CFP | 以下の全てを満たす場合 ・AFP認定者である ・CFP資格審査試験6科目全てに合格する ・CFPエントリー研修の修了 ・FP業務に関し3年以上の実務経験がある(実務経験としてカウントされる研修あり) |
※AFP認定研修の基本課程と技能士課程の違いは割愛します。
上の表の通り、FP1級では実務経験が必要となり、またAFPやCFPは実務経験に加えてや研修を修了する必要があります。よって、独学で取得できるFP資格はFP2級と3級だけになります。
なお、FP2級と3級の違いについてまとめた記事もありますので、合わせてご参考ください。
FP資格を独学で取得するメリットとデメリット

独学でFP3級や2級を取得するにあたり、メリットとデメリットを理解する必要があります。
独学のメリット
FP資格を独学で取得するメリットを2つご紹介します。
- 学習コストを抑えられる
- スケジュールを自由に組むことができる
それぞれについて詳しく解説します。
学習コストを抑えられる
ご自身で購入するテキスト代や文具費用だけで抑えられるため、学習コストはおよそ5,000円程度に収めることができます。
特に、FP試験は過去問が無料で公開されているため、アウトプットも手軽にできるほか、最近ではYouTubeで無料講義を行っているチャンネルもあるため、場合によってはテキストも買わずに合格することも可能です。
スケジュールを自由に組むことができる
予備校などに通う場合、カリキュラムに合わせなければならないところ、独学であればご自身の好きなタイミングで学習できるため、学習管理が得意な人にとっては独学という選択肢も十分にアリだと思います。
独学のデメリット
一方で、独学にはデメリットもあります。ここでは4つご紹介します。
- わからないところを自分で調べないといけない
- テキストを自分で選ばなければならない
- モチベーションの維持が難しい
- 法改正の情報収集が難しい
それぞれについて詳しく解説します。
わからないところを自分で調べないといけない
独学学習で一番のデメリットともいえるのが、わからないところを自分で調べなければならない点です。たとえば予備校では先生や仲間が近くにいるため、わからないところを気軽に質問できるのが強みですが、独学の場合は全て自分で調べる必要があります。
FP試験では知識を問う学科試験だけでなく、計算問題が中心となる実技試験の両方に合格する必要があり、特に実技試験の計算のところでつまずく場合があります。
市販のテキストによっては計算が簡略化して掲載されている場合もあるため、疑問点の解消に苦労をすることがあります。
テキストを自分で選ばなければならない
FP資格を独学で目指す人にとって、テキスト選びもデメリットに感じるでしょう。
現在、大手予備校を筆頭に数多くのFP講座関連書籍やテキストが販売されています。基本的にどのテキストを選んでも合格できると思いますが、テキスト次第で合格までの学習時間や理解の定着度が大きく変わる場合があります。
ちなみに私がおすすめするテキスト選びの基準として、「図解や表が盛り込まれながらも、見慣れない用語に簡単な解説が載っているものを選ぶ」というものがあります。
短い時間で合格するためには、文章メインで構成されているテキストよりも、図解や表がなどが適度に入っているテキストの方がすらすらと読み進められるためです。
中古本などで過去のテキストを購入できますが、できるだけ最新のテキストを購入してください。このあと「法改正の情報収集」について触れますが、FP試験は法改正により制度や内容が変更される場合があります。以前は正解だったものが現在は不正解になることもあり得ます。
中古本やネットショップで過去のテキストを購入しても差し支えありませんが、その場合、最新の情報と突合しなければならないため勉強効率が悪くなります。
モチベーションの維持が難しい
また、独学の場合はモチベーションの維持が難しい点です。現在、FP試験は2級も3級もCBT方式(パソコン形式での受験)に切り替わり、通年受験が可能になりました。
従来の紙方式は年に3回しか受験するチャンスが無かったため、モチベーション維持がしやすかったです。しかし、CBT方式への移行で通年受験できたため、独学の場合、だらだらと学習してしまうリスクがあります。
法改正の情報収集が難しい
そしてもう1つが法改正の情報収集が難しい点です。法改正により、FP試験の内容は毎年少しずつ変更されます(例:国民年金の金額)。そのため、独学の場合は情報のキャッチアップが難しい点もデメリットと言えます。
FP試験を独学で取得する効果的な勉強方法
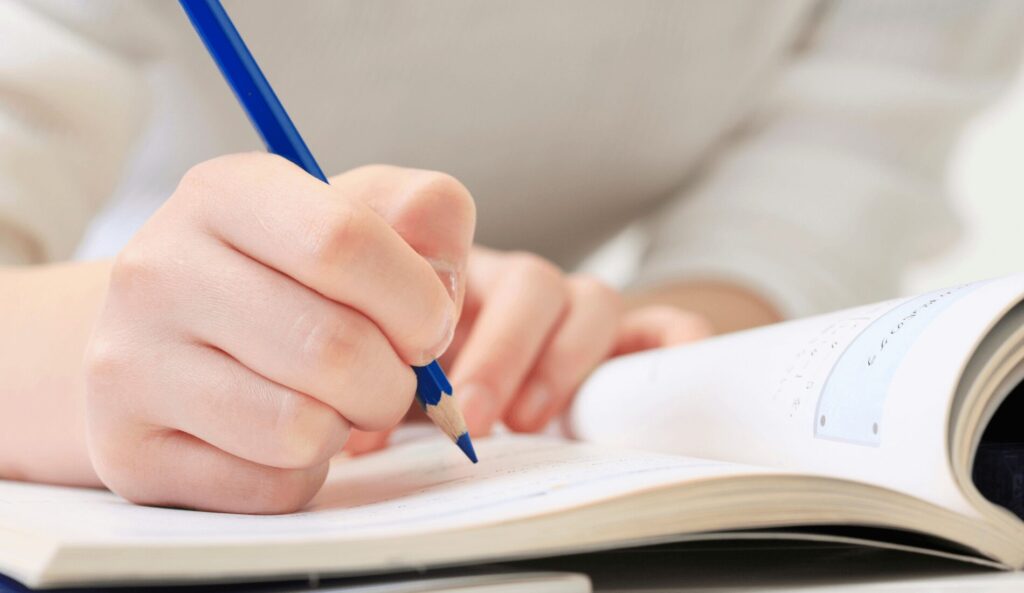
それでは、FP試験を独学で学習する方に向けて、おすすめの学習方法をご紹介します。
次の5つのステップに沿って行うと効果的です。
- 受験日を決める
- 市販のテキストを読む
- FP試験の過去問を解く
- FPのライトの無料問題を活用する
- 勉強の記録をとる
①受験日を決める
まずは、FP試験の受験日を決めることから始めましょう。先ほどもお伝えしましたが、FP2級と3級はCBT方式に移行し、通年で受験が可能になりました。そこで、いつ受験したいか、そしていつまでに資格を取得したいかを決めましょう。
ただし、2つ注意しておきたい点があります。
1つ目が1年のうち受験できない日がある点です。年末年始はもちろんのこと、3月は一切受けることができないため日程は必ず把握しておきましょう。
2つ目が、試験日と合格発表日にタイムラグがある点です。FP試験は受験日の属する月の翌月中旬ごろに合格発表されます。同じくCBT方式が導入されている日商簿記試験はリアルタイムで合否判定されますが、FP試験はリアルタイムで合否判定されません。
そのため、たとえば職場から取得期限を指定されている場合や、就職や転職時の履歴書に記載したい場合は合格発表日を意識して受験しましょう。
| 試験日 | 合格発表日 | 法令基準日 | 合格点 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月1日~4月30日 | 5月19日 | 2024年4月1日 | 学科36点(60点満点) |
| 2025年5月1日~5月24日 | 6月16日 | ||
| 2025年6月1日~6月30日 | 7月15日 | 2025年4月1日 | |
| 2025年7月1日~7月31日 | 8月18日 | ||
| 2025年8月1日~8月31日 | 9月16日 | ||
| 2025年9月1日~9月30日 | 10月16日 | ||
| 2025年10月1日~10月31日 | 11月18日 | ||
| 2025年11月1日~11月30日 | 12月15日 | ||
| 2025年12月1日~12月28日 | 1月19日 | ||
| 2026年1月6日~1月31日 | 2月17日 | ||
| 2026年2月1日~2月28日 | 3月16日 |
②市販のテキストを読む
受験日が決まったら先にテキストを読み、知識のインプットを行いましょう。
たまに「過去問を読んで出題形式を理解してからテキストを読もう」という勉強方法を紹介する記事を見かけますが、これからFP試験を受ける人にとってはこの方法はおすすめしません。
基本的にこの記事を読んでいただいている方は「これからFP試験を受ける!」という方がほとんどだと思いますので、いきなり出題形式を見ても理解の定着には結び付きづらいと思っているためです。
テキストを読んだあとで問題演習を解くというスタンスで問題ありません。
③FP試験の過去問を解く
独学勉強において、過去問演習は必要不可欠です。FP試験では過去問が無料で公開されているため、必ず過去問に挑戦しましょう。
このとき、時間を計測することをおすすめします。理由は学習方法と試験方法が異なるためです。日ごろの学習はテキストとノートで行いますが、実際の試験はCBT方式(パソコン形式)になります。
そのため、普段から時間配分に慣れておくことでCBT方式にもスムーズに対応できます。
④FPのライトの無料問題を活用する
独学でFP試験を勉強するかたにオススメしたいのがFPのライトの無料問題です。こちらはFPのライトが近年の出題傾向や押さえておきたいポイントを網羅した問題を多数ご用意しているコンテンツです。
セクションごとに独自で設定した制限時間を設けており、制限時間内で解くことができれば合格にぐっと近づくことを意味しています(制限時間は少し厳しめに設定していますので、時間オーバーになっても自信を持ってください!)。
どなたでもPCやスマホから無料で挑戦できるので、独学のかたはぜひ積極的に活用しましょう!
\制限時間付き!苦手分野を集中して克服!/
無料問題終了後、解答とワンポイントアドバイスを表示されるので学習の参考にしてください!
なお、解説は表示されません。無料問題の質問や解説は「FPのライトの通信講座の受講者限定」特典となります。
⑤勉強の記録をとる
そして、テキストや過去問で学習したらぜひ勉強の記録を取りましょう。問題演習でも十分アウトプットの効果がありますが、それを別のツールなどに書き込むことで、学習の振り返りがしやすくなるだけでなく、更にアウトプットの質が高まります。
ちなみに、以下の項目を記録しておくと良いでしょう。
- 勉強日時
- 学習範囲(ページや章)
- 学習した知識(用語や計算方法など)
- 得意と感じたところ
- 難しいと感じたところ
これらを記録しておくと、得意範囲と苦手範囲をいつでも見返すことができるため、忘れにくくなります。
ここで、私がオススメする記録方法を3つ紹介します。
Studyplusに記録

まずはStudyplusで記録する方法です。私も2級と3級の学習管理の際にStudyplusに記録していました。日々の学習を記録できるだけでなく、試験日を設定し試験日までのカウントダウンをしてくれるため、進捗管理やモチベーション維持に便利です。
XやInstagramなどのSNSに投稿
次に、XやInstagramに学習内容を投稿する方法もおすすめです。他のユーザーが閲覧できる媒体に学習範囲や時間を記録する習慣をつけることで、サボりづらい環境を作ることができます。
また、SNSに投稿するメリットとして、同じFP試験をの合格を目指す仲間とコミュニケーションをとれる点があります。独学の場合はモチベーション維持に苦労する場面が多いですが、気軽に仲間とやり取りができるSNSを活用することで、「もう少し頑張ってみよう!」とポジティブにとらえることが期待できます。
Notionに記録

そして、Notionもおすすめです。Notionとはメモやタスク管理、ドキュメント管理など生活や仕事で使うツールを1つにまとめたサービスです。無料でもさまざまな機能を利用できるため、私はタスク管理やメモ、学習記録も全てNotionで管理しています。タイマー機能やカレンダーとも連携できるため、最近の私はNotion一択です。

記録方法に正解はありません。正直なところペンとノートで完結させてもOKです。記録をすることは勉強した内容の理解を深め、モチベーションを維持するための手段です。
記録方法にこだわることも大事ですが、いかにご自身の勉強スタイルに合うかどうかという視点を忘れないようにしましょう。
勉強時間を確保しよう
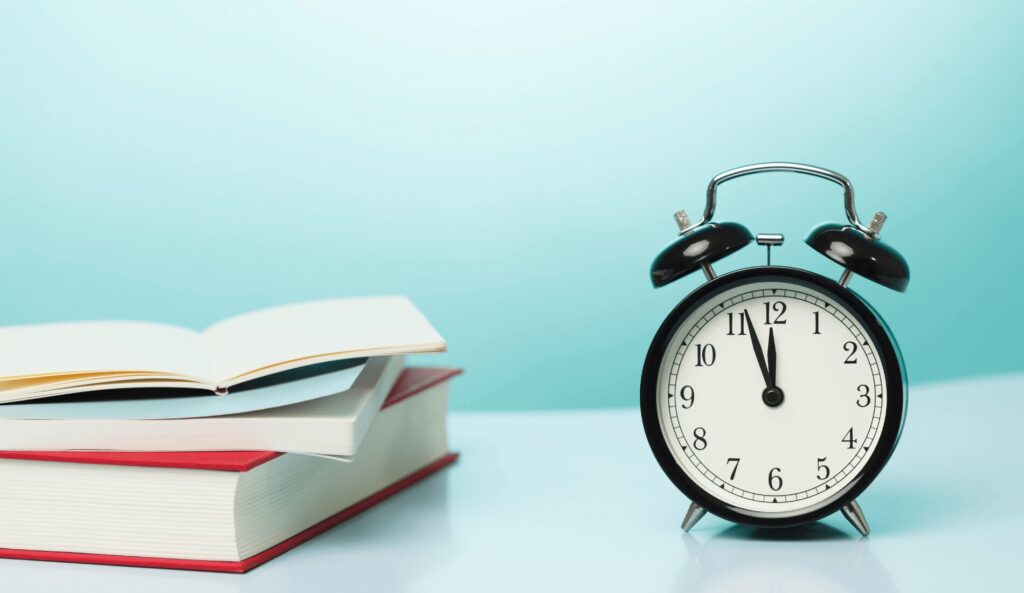
独学の場合、勉強時間の確保が特に重要になります。ご自身の受験日を決めたら、次に紹介する勉強時間の目安を参考に勉強を進めていきましょう。
FP3級の勉強時間(目安)
FP3級の合格に必要な勉強時間は、およそ80時間~100時間程度とされています。そのため、仮に1日2時間勉強すると、40日~50日程度で合格できることになります。
FP2級の勉強時間(目安)
FP2級の合格に必要な勉強時間は、およそ150時間~200時間程度とされています。仮に1日2時間勉強すると、75日〜100日程度で合格できることになります。

【FP3級/FP2級】テキストを買うベストなタイミングとは?

ここまで記事をお読みいただき、FP3級の解像度が高まってくれば、あとは勉強を始めるだけ!しかし、まずはFP試験用のテキストを購入するところから始めなければなりません。
では、実際のところテキストを買うタイミングはいつが良いのでしょうか。それは、あなたが受験する日を先に決めて勉強時間を逆算して決めた日が買うタイミングとしてはベストになります!
具体的には、FP3級を受験する場合は試験予定日の1ヵ月~1ヵ月半前にテキストを購入し、FP2級を受験する場合は試験予定日の2ヵ月半~3ヵ月前にテキストを購入するのがよいでしょう。
先ほどもお伝えした通り、FP3級の勉強時間の目安はおよそ80時間~100時間程度で、FP2級の勉強時間の目安はおよそ150時間~200時間程度あれば十分合格ラインに達することができます。
加えて、FP試験は2級も3級もCBT方式(パソコン形式での受験)に切り替わり、通年受験が可能になったことから、あとは皆さんご自身で受験する日を決め、目安となる勉強時間を逆算すればおのずとテキストを購入するタイミングが見えてくるでしょう。
独学での勉強が難しいと感じたら、FPのライトの通信講座を活用しましょう
FP試験は独学での合格が可能であることはお伝えした通りです。しかし、市販テキストの選定や学習管理、わからないところを解決するのも全て自分自身で取り組まなければなりません。
もし独学で勉強するのが難しいと感じた方は、FPのライトの3級講座がおすすめです。
FPのライトは2,980円でテキストと演習問題がセットになっているため、費用を抑えながらもFP3級の取得を目指したい方におすすめです。通常、市販テキストと問題集だけでも3,000円を超える場合がほとんどです。その中でテキストと演習問題が一体となり、さらにわからないところもLINEで質問できる仕組みは他にないコスパ最強コンテンツです!
2,980円で最短合格!
まとめ
FP資格の独学は、正しい教材選びと計画的な学習を行えば十分に合格可能です。特に3級・2級は独学者にとって取り組みやすく、費用を抑えてスキルアップを目指せます。自分の目的に合った学習方法を選び、効率よく合格を目指しましょう。
しかし、独学はテキスト選びや学習管理、わからないところを自分で解決しないといけないなどのデメリットもあります。
独学を検討する際はこれらのデメリットを理解した上で、もし難しいと判断した場合はFPのライトの通信講座などの活用を検討し、最短で合格できるようにしましょう!


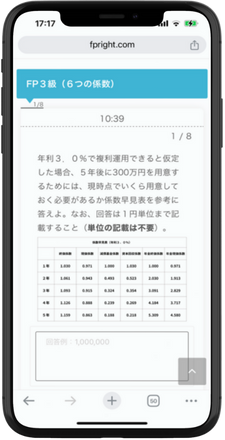

とはどんな資格?注目される理由と取得方法を解説-485x281.webp)